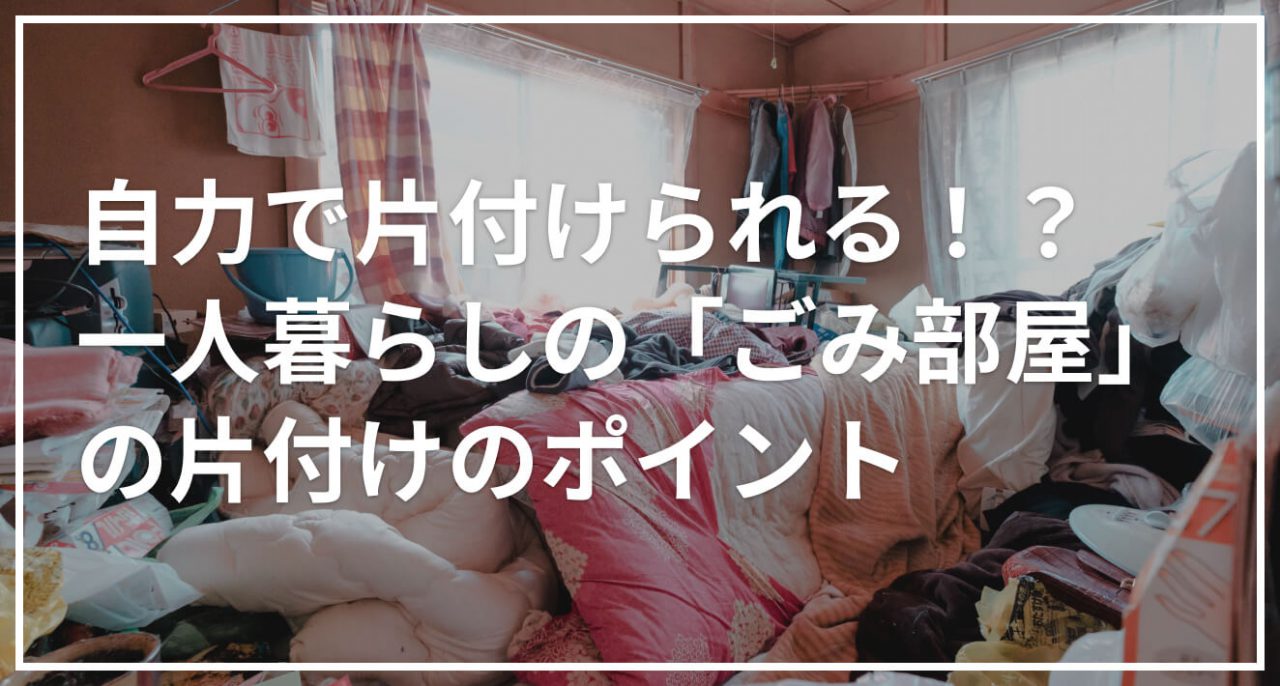「ごみ部屋になってしまった自分の部屋を片付けたいけど、どうやって片付ければいいか分からない」「片付けるのが本当に苦手で、ごみ部屋の片付けがなかなか捗らない」…。弊社エバーグリーンにも、様々なご事情やお悩みを持ったお客様から、ごみ部屋の片づけについてご相談を受けることが多いです。
そこで今回は、1Rや1K、1DKなどの一人暮らしの部屋を想定して「ごみ部屋」の片付け方のポイントについて、分かりやすく解説していきます。
ごみ部屋の片付けを始める前の準備や確認

ごみ部屋の片付けは、しっかりと計画を考えて綿密な準備を行なうことが、最後までキッチリと片付けるためのポイントです。まずは、ごみ部屋の片付けを始める前の準備や確認についてご説明します。
①自治体の「ごみの排出ルール」を確認
ごみ部屋を片付けよう!と心に決めたら、自治体の「ごみの排出ルール」をまず確認しましょう。ごみ部屋を片付けていくと、ごみが大量に発生します。部屋が広くてごみ袋を大量に置いておけるスペースがあれば良いですが、部屋が狭いと片付けや生活の邪魔になってしまいます。特に多く発生するのは「燃えるごみ」ですから、発生した燃えるごみをすぐに捨てられるよう、ごみ部屋の片付けは「燃えるごみの日」の前日に始めるのがおすすめです。
また、後ほどご説明しますが、ごみ部屋の片付けはなるべく大きなものから手を付けるのが鉄則です。そのため、もし大きめの家具や家電などを捨てたい場合には、「粗大ごみ」の排出ルールについても必ず確認しておきましょう。基本的には集積場に出せばよい燃えるごみとは異なり、粗大ごみの排出ルールは自治体によって違いがあります。例えば、エバーグリーンの本社がある木更津市では、家庭の粗大ごみはクリーンセンターに電話予約をして戸別収集を依頼するルールになっています。自治体によってはシール状の排出券を買って粗大ごみに貼るルールになっているところもあるので、注意してください。
もちろん、ごみの分別ルールや各種類のごみの収集日、指定ごみ袋の種類について確認しておくことも大事です。ごみが適切に分別されていなかったり、収集日以外にごみを出したり、指定ごみ袋以外の袋で出したりすると、ごみが収集されずに他の住人等に迷惑になってしまいます。
②掃除道具を準備
ごみ部屋のごみを片づけた後には、必ず部屋中を掃除する必要が出てきます。そのため、掃除道具を準備することも大事です。部屋を片付けていくとホコリやチリなどの細かなゴミは必ず発生しますし、もし食べ物や飲み物などが床にこぼれていたら、洗剤を使って拭き掃除をする必要があります。また、キッチンやトイレ、風呂などの水場を掃除する場合は、それぞれに適した掃除道具や洗剤が必要になります。
基本的な掃除道具を表にしてまとめてみましたので、参考にしてみてください。なお、掃除道具を買う時には、ホームセンターやドラッグストアであれば一通り揃えられるので、おすすめです。
| 捨てても構わないシャツ・パンツ | ごみ部屋の掃除を行なうと、ひどく汚れたりキズが付いたりすることがあります。捨てても構わないシャツ・パンツで臨みましょう。 |
| ゴミ袋 | 自治体指定のゴミ袋を用意しましょう。大きなサイズを多めに。ゴミ袋は生活の中で必ず消費するものなので「買い過ぎ」にはなりません。 |
| ビニールひも | 本や雑誌、新聞、段ボールなどの紙資源をまとめるのに必ず必要になります。 |
| 雑巾 | 拭き掃除に必要になります。店で購入してもいいですし、古くなったタオルを代用するのでも良いです。 |
| フロアワイパー | 床の仕上げ掃除に必要になります。100円ショップにもありますが使いづらいこともあるので、有名なメーカーのものがおすすめです。 |
| ほうき・ちりとり | ごみ部屋掃除の場合には、掃除機よりもほうきで掃く方が効率的だったりします。コンパクトサイズのものでOKです。 |
| 軍手 | 家具・家電類を持ち運んだりするのに必要です。また、ごみ部屋に積み重なった物を選別する時にも、あると意外と便利です。 |
| ビニール手袋 | トイレ、風呂、キッチンなどの水場を掃除する時に使います。使い捨てのたくさん入っているものがおすすめ。 |
| 洗剤(トイレ用、風呂用、キッチン用、リビング用) | トイレ、風呂、キッチン、リビング、それぞれ汚れの性質に違いがあります。それぞれの性質にあった洗剤を用意しましょう。 |
| ブラシ類(トイレ用、風呂用) | 準備し忘れがちですが、それぞれ掃除には欠かせないアイテムです。 |
| スポンジ(キッチン用) | 汚れが酷い場合には何個も必要な場合も。生活の中でも消費するものなので、多めに準備しておきましょう。 |
③手伝ってもらえる人がいないか考える
部屋の散らかり具合やごみの量にもよりますが、「ごみ部屋」を片付けるのは思っていたよりも重労働になることが多いです。そのため、もし部屋に人を入れるのに抵抗がなければ、手伝ってもらえる人がいないか考えてみるのも良いでしょう。
もし、知っている人に手伝ってもらうのは抵抗がある場合には、専門業者に依頼するのも有効な手段です。専門業者に依頼すれば掃除道具を自分で用意する必要はありませんし、ごみの処分も依頼できるので、労力をかけずに部屋を片付けられます。
ごみ部屋の片付けを効率的に進めるための3つのポイント

準備ができたら、いよいよ片付けに入ります。とはいえ、何から手を付ければいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、片づけを効率的に進めるためのポイントを3つご紹介します。
ポイント1.明らかなごみを片っ端からごみ袋に放り込んでいく
ごみ部屋の片付けは、まずはごみ袋を片手に部屋の中を見渡して、「明らかごみ」から片っ端にごみ袋に放り込んでいくことから始めましょう。
「ごみを分別しながら放り込む」か「分別せずに片っ端から放り込む」の2パターンがありますが、特に一人暮らしの広くない部屋の場合には、一度放り込んだごみをまた分別しようとすると部屋が散らかってしまうことになるので、
最初は「燃えるごみ」
次に「ペットボトルごみ」
最後に「燃えないごみ」
といった具合に、片付けるごみの種類を決めながら放り込んでいくことをおすすめします。
ごみの片付けさえ済んでしまえば、後の作業は要るものの整理と掃除だけになります。逆を言えば、ごみの片付けが終わらないうちに整理や掃除をしてしまうと、作業が捗らないばかりか、中途半端に終わってしまい、すぐにごみ部屋に逆戻りしてしまうことも。まずは要らないものを徹底的に部屋から無くしてしまうことが、ごみ部屋の片付けの重要なポイントです。
ポイント2.「玄関への動線」の確保を目標にする
2つ目のポイントとして、玄関への動線を確保することを目標にしましょう。
なぜ「玄関への動線」が大事なのかというと、これはつまり「ごみ排出のルート」の確保のためです。粗大ごみや大きなごみ袋を排出するには、人がしっかりと踏ん張りながら歩けるスペース(足の踏み場)が必要です。特に粗大ごみを出す場合には、それなりに広い空間が必要になりますから、まずは玄関までの道をしっかりと確保するようにしてください。
片付けが一日で全て終わるのならば良いですが、ごみの量によっては何日もかかる場合もあります。そういった場合も想定しつつ、出せるごみはどんどん出して部屋の中を広くしていくのが、片付けを効率的に進めていくためのコツです。
また、特に1Rや1Kの部屋の場合には、リビングから玄関への動線までに、キッチンやトイレ、風呂などの設備があることがほとんどです。玄関への動線を確保すれば、自然とキッチンやトイレ、風呂などの片付けにも着手しやすくなります。
ポイント3.「大きなもの」は処分できないか検討する
3つ目のポイントが、家具や家電などの「大きなもの」を処分することです。
不要な家具や家電などを片付けてしまうことで、動けるスペースが広くなり片付けを進めやすくなります。また、家具や家電を思い切って捨ててしまうことで、片付けをした後もスッキリとした空間を維持しやすくなります。
ただし、部屋がごみだらけのままで大きなものを動かそうとすると、転倒したり無理な姿勢になって身体を壊す危険があります。そのため、無理なく動かせる環境になるまでは、ごみを片っ端から放り込む作業を優先することをおすすめします。
下表に、特に一人暮らしの場合に必要か不要かを判断すべき家具・家電等をまとめてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。なお、家具や家電類の捨て方については、自治体のルールを必ず確認しましょう。
| 家具類 | |
| タンス・衣装ケース類 | タンスがいくつもある場合は、中にしまっている衣類を減らしてタンスを減らせないかを検討してみてください。 |
| カラーボックス・本棚類 | 本や漫画、雑誌類も本当に必要なもの以外は処分を検討して、それらを収納する家具を減らせないか考えましょう。本や漫画、雑誌類をスキャンしてデータ化するのも片付けには有効。 |
| ソファ | 1Rや1Kの広くない部屋の場合には、ソファは大きすぎることがほとんどです。こだわりがない場合はコンパクトな座椅子や座布団に替えてしまいましょう。 |
| ベッド | 1Rや1Kの広くない部屋の場合には、ベッドが部屋の多くを占めてしまいます。なるべくコンパクトなサイズのものや折り畳み可能なタイプのものに替えられないか検討してみましょう。思い切って処分して、スノコマット+布団の組み合わせに替えるという手段も。 |
| スツール | ものを収納しつつイスにもなるとして効率的な家具ではありますが、いつの間にか要らないものがギッシリ詰まった不要物になってしまっていることも。中身を見直し、必要最低限のもの以外は処分してしまいましょう。 |
| 家電類 | |
| 故障しているもの | 本当に必要なものであればすでに直して使っているはず。故障したまま放置してあるものは必要ないものなので、捨てましょう。 |
| 電気ポット | 一人暮らしであれば、ヤカンで十分なことがほとんどです。 |
| コーヒーメーカー、エスプレッソマシン | サイズが大きくかさばる割に、使い道が限定されています。毎日のように使っているようでなければ、捨ててしまって問題ありません。 |
| 掃除機 | 1Rや1Kなどの広くない部屋の場合には、クイックルワイパー等で十分だったりします。思い切って捨ててしまって良いでしょう。小型のものに買い替えるというのも手。 |
| 扇風機・こたつ | 特定の季節にしか使わない割に、意外とかさばり仕舞う場所にも困りやすいです。どちらも部屋にエアコンがあればそれで十分なので、捨ててしまいましょう。 |
| 使っていないノートパソコン、タブレット | 新しいものを買ったときに古いものを予備として残しがちですが、実際に予備として使うことはほとんどありません。必要なデータを取り出した上で処分しましょう。 |
| プリンター | 毎日、毎週のように紙を印刷している人以外は、捨ててしまって問題ありません。最近はどのコンビニにも多機能プリンタがあり、USBなどにファイルを保存して持って行けば印刷できるので、そちらを使いましょう。 |
| コンボ・スピーカー | 実は使っていないことが多いのではないでしょうか。映画や音楽鑑賞が趣味でない場合には、捨ててしまっても問題ないことが多いです。また、一人暮らしの場合は騒音問題の原因になることもあるので、今一度必要性を見直しておきましょう。 |
| ランニングマシン・エアロバイク | もし使っている場合でも、捨てるのを検討してほしい家電です。外を走ったり、自転車をこいだりするのに替えられれば、その分部屋の中を広くできます。また、一人暮らしの場合は騒音問題の原因になることもあるので、今一度必要性を見直しておきましょう。 |
ごみか否かを判断するための3つの基準

ごみ部屋を効率的に片付けるための3つのポイントとして「ごみを片っ端からごみ袋に放り込んでいく」ことを先述しましたが、実際にやってみると「どれが不要なのかが判断できない!」という方も多いでしょう。そこで、「これならば処分しても問題ない」という基準を3つ、ご紹介します。
基準その1.1年以上使っていないものは処分する
1年以上使っていないものは、生活には不要なものと言うことができるので、たとえ「まだ使える状態」であっても捨てることを検討しましょう。
特によく見ていただきたいのが「衣服類」です。衣服類は購入する時にはかさばらず、かつ買う時には「これは着る!」と思って購入するものなので、気付かないうちに大量にストックされてしまう性質があります。ところが、実際に普段から着ているものはそう多くはないはずですし、また衣服類には旬やシーズンがあるので、一度着なくなったものがリバイバルすることもほとんどありません。本当にお気に入りでずっと手元に残しておきたいものや、普段からよく着用しているものを除いて、処分の対象として検討してみてください。
また、本や漫画、雑誌類も1年以上読んでいなければ、これから先も読むことはないと考えて良いでしょう。これらも衣服類と同様、気付いたら大量にたまっていて収納スペースを圧迫していることが多いので、片付けのタイミングで全て「必要」か「不要」かに仕分けてしまってください。
ちなみに本や漫画、雑誌類、衣服類の場合、「捨てる」以外にも古着屋や古本屋、フリマアプリで「売る」という処分方法も有効です。特に衣類は、一度は気に入って購入している分、捨てるのは心苦しいと感じることもあるでしょうから、そういった場合は売ることで、他の誰かに愛用してもらうと良いでしょう。
基準その2.複数あるものは使う分だけを残す(予備を持たない)
ごみ部屋にありがちなのが、同じ使い道の物がたくさんあって収納しきれなかったり、部屋中に散らばって片付かないという状況です。しかし一人暮らしであれば、物は基本的には1つあれば足りるはず。例えばお茶碗やコップなどの食器類は、いくつもあったとしても食事の時には1つしか使いません。お客さんが頻繁に尋ねてくるような場合は予備があっても良いですが、そうでない場合は余計な分を思い切って処分しましょう。
食器類のほかにも、例えばスマホ・タブレット用の充電器やコード類、筆記用具・小物類などがたくさんたまりがちです。これらも食器類同様に、基本的には一度に1つしか使わないはずですから、使う分以上のものは処分を検討してください。
基準その3.また手に入れられるものは処分してよい
1年以上使っていないものや、いくつもあるものを片付けたら、「使うといえば使うし、使わないといえば使わない。かといって大事かといえばそうでもない」という微妙な立ち位置のものが最後に残るはず。そこで、とどめの判断基準としておすすめなのが「また手に入れられるものは処分する」という基準です。
例えば「これは絶対読みたい!」と思って購入したけど、結局読んでいない本があるとします。ずっと読んでいないけど「読みたい」気持ちは強かっただけに、中々処分する踏ん切りがつかなかったりしますが、そもそも「本」であれば絶版になっていない限り、一度処分してもまた買い直すことができますよね。このように「その気になればまた手に入れられるもの」は思い切って処分してしまいましょう。
ちなみにこの3つ目のポイントは、趣味の分野の物の片付けに有効です。例えば好きなアーティストのグッズを断捨離したい場合。グッズは、コンサートやイベントなどでしか手に入れられないなどの「限定物」と、CDやブルーレイ、本などといった「限定ではない物」の2種類に分けられます。限定物は一度手放すとまた入手するのは難しいので、よほど大量でなければ保存しておいて良いです。そうでない物は思い切って、処分を検討してみてください。特にCDは今の時代、パソコンにデータとして取り込み、それ以降は使わないことが多いはずです。
どうしても自力で片付かなければ、専門業者に依頼しよう
今回は、1Rや1K、1DKなどの一人暮らしの部屋を想定して「ごみ部屋」の片付け方のポイントについて解説してきました。
どうしても自力では部屋が片付かない、部屋を片付けるための時間がない、もっと楽に部屋を片付けたい!といった場合には、ぜひ専門業者に依頼することをおすすめします。
エバーグリーンでは、荷物の整理・整頓から大量の不要物の処理、各種特殊清掃に至るまで、様々な片付け・清掃作業を承っております。
片付け・清掃作業についてお悩みの方はぜひ、エバーグリーンまでご相談ください。
周囲の人にまで迷惑をかけるほどのゴミ屋敷になってしまう原因は、病気にあることも少なくありません。
ゴミ屋敷ではかなりの悪臭や害虫が発生しており、まともに住める状態では無いことが多々あります。
しかしそんな環境でもゴミを捨てない人の心には、病気などのトラブルがあると考えられるでしょう。
少し片付けが苦手なだけ、という理由で済まない状態なら、ゴミ屋敷化に繋がる可能性のある病気について知っておくことをおすすめします。

この記事について
大邑政勝
- 家財整理専門会社エバーグリーン 代表
- 一般社団法人 家財整理相談窓口 理事
- 一般社団法人 日本特殊清掃隊 理事
特殊清掃、遺品整理、火災現場復旧など10年にわたる現場経験と多種の資格を有し、豊富なノウハウで顧客第一のサービスの提供に努める。